検定試験作成サービスとは?自社のノウハウを活用した資格制度の構築方法
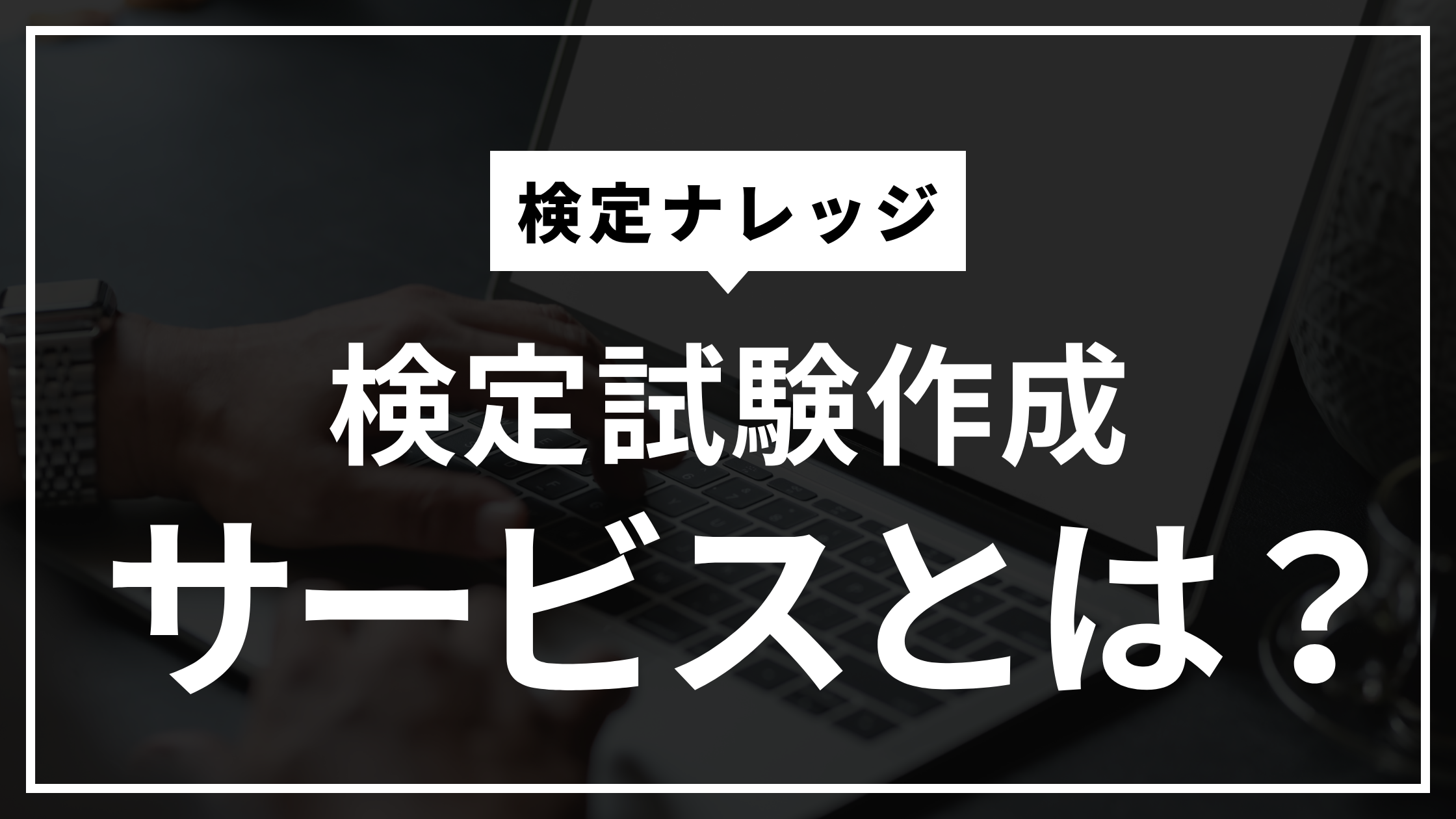
企業の競争力を強化し、社員のスキルを向上させる手段として、検定試験や資格制度の導入が進んでいます。
しかし、自社で質の高い検定試験を作成し運営するには、専門知識やノウハウ、そして多大な時間と労力が必要です。
この作業は企業にとって大きな負担となります。
そこで注目されているのが「検定試験作成サービス」です。
これらのサービスは『試験の企画・設計から問題作成、実施、採点、結果分析まで、検定試験』の全プロセスを専門家がサポートします。
スキルを客観的に評価し、社員育成につなげるにはどのような方法があるでしょうか?
企業が独自目線で試験を作成することで、スキルの可視化や教育制度の強化が可能となります。
本記事では、検定試験作成サービスを活用し、自社のノウハウを体系化した資格制度を構築する方法について解説します。
検定試験作成サービスとは?

検定作成サービスとは、企業や教育機関、個人の目的に合わせて検定試験を作成し、実施するサービスです。
検定試験の企画や開発から作成、採点、結果通知まで試験の運営に関わる一連の業務を支援します。
このようなサービスを利用することで、企業の業務過多を防ぎ、効率的な検定試験などを運営することが可能です。
企業が検定試験を導入する理由
近年、多くの企業が検定試験を導入しています。
検定試験を導入する企業が増えている理由にはどういったものがあるのでしょうか。
①人材育成や評価の効率化
- 社員のスキルや知識レベルを客観的に評価でき、適切な育成計画や人材配置をおこなうことができます。
- 検定試験の結果を昇進や昇格などの評価の指針として活用が可能です。
- 公平性や客観性をもって利用することができます。
②教育システムの一環として
- 検定試験を導入し合格することで、従業員のスキルアップを客観的に証明することが可能です。
- 従業員の自信やモチベーションを高めることができます。
- リモートワークやフレックスタイム制を採用している企業において、従業員が個々のペースでスキルを向上させます。
③企業イメージや信頼性の向上
- 検定試験に合格することで、顧客に対しての安心感や信頼感を与えるだけではなく、企業の専門性や品質をアピールすることができます。
検定試験を導入するメリット

企業が検定試験を導入するメリットとして、従業員の教育やモチベーション向上に効果があることを述べさせていただきました。
では、その他に導入するメリットはなにがあるのでしょうか?
社員のスキルを標準化・可視化できる
検定試験をおこなうことで、従業員のスキル向上やモチベーション向上につながります。
このことにより、業務のミスが減り生産性が向上します。
モチベーション向上と組織力強化につながる
スキルアップの機会を提供をすることで、従業員自身がキャリアアップについて認識することが可能です。
企業側も試験結果より育成計画を作成でき、組織全体で会社への満足度があがります。
このことにより、離職者を減らすことができます。
外部向け資格として企業ブランドの向上も可能
従業員のスキル向上により、企業の専門性や品質の高さをアピールできます。
顧客に安心感を与えることもでき、企業全体のレベル上げにも役立つのです。
検定試験の作成手順とポイント

企業で検定試験をおこなう際、試験を適切に設計、運営することで従業員のスキル向上や企業の成長につなげることができます。
検定試験の作成手順やポイントをご紹介します!
作成手順
①目的の明確化
何を評価する試験なのか?なぜ試験を実施するのか?目的を具体的に設定します。
目的を明確化することで、試験内容や難易度、評価の基準を適切に設定が可能です。
例:従業員のスキルの把握、特定の知識やスキルの習得促進、昇進、昇格の基準など
②試験範囲と対象者の決定
誰を対象者とした試験なのか、対象者の決定をおこないます。
また、試験範囲も明確にし社内のマニュアル、資格要件、研修内容を参考に範囲を設定が可能です。
例:業務に必要な知識、特定のスキル、コンプライアンスに関する知識など
③試験の形式、問題を決めます
試験形式を決めます。
- 択一選択(○×や選択)
- 記述式
- 実技試験
- 面接方式
- オンライン試験(e-ラーニングなど)
問題を作成するにあたり必要となるポイントです。
- 客観性と公平性
- 難易度のバランスを考える(基礎、応用など)
- 実際の業務で発生するケースを想定した内容
⑤評価基準の明確化
自動採点できる場合と、主観的評価が必要な問題のバランスを考えます。
試験結果から受験対象者の従業員へのフィードバックをおこない、成長へ繋げることが可能です。
⑥試験の実施と結果分析
試験実施日、実施期間の通知や場所、試験方法を通知します。
試験実施後、採点が必要な場合、採点をおこない合否を通知し、教育計画に反映します。
個人、部署ごとにフォローアップ研修を実施し、試験の難易度が適正であったか、妥当性を見直し次回試験につなげていきましょう。
検定試験作成サービスの選び方
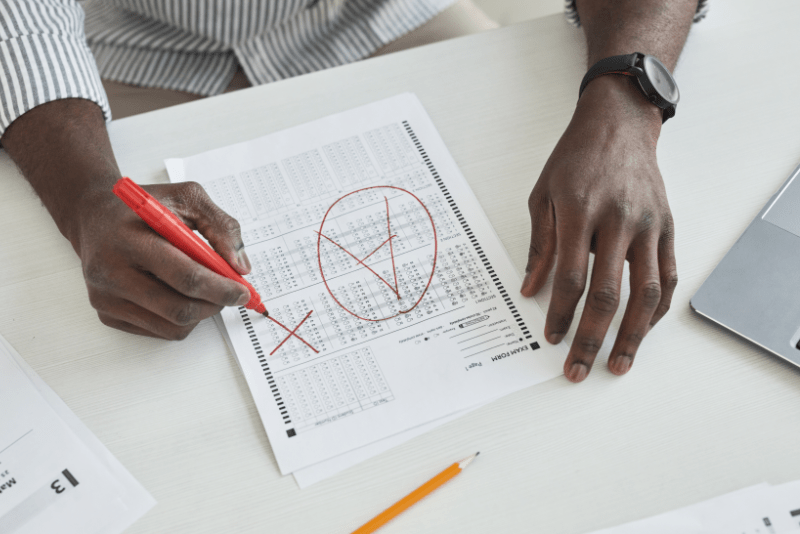
企業が検定試験作成サービスを選ぶ際にも確認すべきことがあります。
- 試験の目的に合った機能があるか
- 不正対策や採点・分析の効率化が可能か
を確認することが重要です。
作成ツールの活用 vs. 外部業者の利用
作成ツールの利用と外部業者への依頼は、それぞれメリット・デメリットを持っており、どちらを選ぶかは企業のニーズによって異なってきます。
作成ツールと外部業者への依頼、それぞれどちらがいいのでしょうか?
作成ツールを使用
- メリット
①コストの削減
外部の業者に依頼するよりも、費用を抑えられる場合があります。
②カスタマイズが可能で、柔軟性がある
自社の業務内容に合わせて、問題作成や変更が可能です。
試験の形式も選択可能で、柔軟性があります。
- デメリット
①専門的な知識が必要
試験作成に関するスキルや知識が必要で、適正な試験の作成が難しい。
②セキュリティリスク
情報セキュリティ対策を自社でおこなう必要があります。
一部のツールでは監視機能など、ツールが不足していることも。
- 向いているケース
- コストを最小限に抑えたい
- 試験頻度が高く、柔軟かつ迅速な対応が必要
- 既にノウハウやツールが存在しており、試験の内容がシンプルである
外部業者に依頼する場合
- メリット
①専門家が設計作成するため、品質が高い
試験作成のプロが作成するため、高品質な試験を作成できます。
公正で信頼性の高い試験の作成が可能です。
②不正対策が充実している
専門業者によるセキュリティ対策が期待できます。
監視機能付きのオンライン試験を導入しやすい。
③企業の負担が軽減できる
試験の設計から運用、採点まで業者がおこなうので、企業側での負担が軽減されます。
- デメリット
①コストが高い
初期費用+カスタマイズの費用がかかり、都度別途料金がかかる場合もある。
②柔軟性が低くなる
試験内容や形式のカスタマイズに制限がある場合があり、変更依頼をするたびに時間とコストがかかる。
- 向いているケース
試験規模が大きく、自社での対応が難しい場合
セキュリティ対策を重視する場合
試験作成や運用を外部委託したい場合
試験の内容や規模、目的や予算などの要素に合わせ、総合的に考慮し選ぶことが重要です!
運用サポートの有無(採点・合否判定システム)

検定試験サービスを利用する際、運用サポートの有無、どこまでやってくれるかは重要な要素ですよね。
多くのサービスは様々なかたちでサポートを提供しています。
運用サポート種類
①基本的な運用サポート
試験会場の準備や運営、監督
オンライン試験システムの運用
各種、問い合わせ対応
②採点、評価サポート
採点の代行、結果の集計や分析、評価レポートの作成
③システム運用や保守
トラブルシューティングやセキュリティ対策
オンライン試験でのシステムの保守や管理
料金プランと導入コストの比較
| 会社 | 概要 | 価格 | URL |
|---|---|---|---|
learningBOX | ・グレードによりできる事が異なる ・フリープラン有 ・不正対策はスタンダード以上 ・eラーニングに対応 | フリープラン~ ¥198,000 | https://learningbox.online/ |
AirCourse | ・フリープラン有 ・サポートはベーシック以上 ・コンテンツが豊富 ・eラーニングに対応 | 要相談 | https://aircourse.com/ |
etudes(エチュード) | ・コンテンツが豊富 ・難易度が低め ・eラーニングに対応 | 要相談 | https://etudes.jp/ |
| JAGATオンライン 試験システム | ・多くの検定を企画・開発 ・不正対策に強い ・創業年度が古いため数多くの実績有 | 要相談 | https://www.jagat.co.jp/ |
| Leaf Exam Operation(LEO) | ・コンテンツが豊富 ・eラーニングからストレスチェックまで対応可能 | ¥87,500~ ¥680,000 (税抜) | https://www.insource.co.jp/it-tool/leaf-exam-operation.html |
検定試験サービスは数多くあるため、自社に合った企業を比較し申し込みをすることをおすすめします。
まとめ
検定試験を導入する際、目的や対象者に応じて適切な試験形式を選ぶことが重要です。
最適な試験の形を決定しましょう。
①試験の目的を明確にする
- 従業員の業務スキルを測定し、研修や昇格の基準とする。
- 社内資格や認定制度を設け、スキルの証明として活用する。
- 人材育成の判断材料として利用する。
- 研修の理解度を確認し、従業員のモチベーション向上につなげる。
② 試験の形式を選ぶ
- 選択式(○×・多肢選択):短時間で多くの受験者を評価でき、採点の自動化が可能。
- 記述式:論理的思考や表現力を測るのに適しているが、採点負担が増える。
- 実技試験:業務スキルの実践力を評価できるが、運営コストがかかる。
③ 試験の運用方法を決める
- オンライン試験:場所や時間を問わず受験可能。不正防止機能の有無を確認。
- 対面試験:監督付きで信頼性の高い試験運用が可能。
④試験の頻度と合格基準を設定する
- 定期試験(年1回・半年に1回):スキルの維持・向上を目的とする。
- 随時試験(オンデマンド):受験者の都合に合わせ、必要なタイミングで受験可能。e-ラーニングなど
- 合格基準の設定:平均点ベース・段階評価(初級・中級・上級)など、自社に合った基準を決める。
⑤運用負担とコストのバランスを考慮する
- 自社で試験を作成・管理:低コストで運用可能だが、試験設計のノウハウが必要。
- 外部サービスを活用:専門家のサポートを受け、信頼性の高い試験を実施。
検定試験を成功させるには、目的・形式・運用方法・頻度・コストのバランスを考慮することが重要です。
業務に最適な試験を導入し、社員のスキル向上や適切な人材配置につなげていきましょう。

コメント